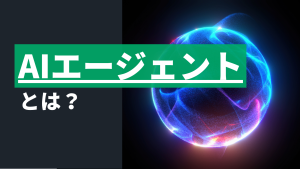当社は、5回目となる年次オブザーバビリティ予測レポートを発表しました。このレポートは、世界中のエンジニアリングおよびIT分野のリーダー1,700人を対象とした調査を基にしています。本レポートでは、到来するテクノロジー時代における成功を形作る能力、ビジネス成果、事業運営上の課題について探ります。
インテリジェントオブザーバビリティとAIの台頭
AIが人々のあらゆる活動に浸透しつつある今、テクノロジーの世界は再び大きな転換期を迎えようとしています。この新しい時代では、従来の基本的な監視からインテリジェントオブザーバビリティへの移行が求められます。つまり、ソフトウェアが大規模に拡大し、経験豊富なエンジニアから非IT分野の専門家まで、誰もがアプリケーションを素早く構築し導入できる環境に備える必要があります。今後訪れる転換の規模と複雑さは前例のないものであり、従来のオブザーバビリティでは対応が困難です。オブザーバビリティそのものが、誰にでも利用できるようになる必要があります。
私たちの調査によると、AI監視の導入率は2025年には54%と、2024年の42%から増加しています。この2桁成長により、AI監視を導入した組織が初めて過半数に達しました。組織はAIの単なる試験段階を超え、顧客が関わる実際の環境での導入を進めています。この移行により、組織は隠れた障害を防ぐため、複雑な分散システムの動作や相互関係に関するリアルタイムの洞察を必要としています。その結果、より深いオブザーバビリティへの需要が高まっています。
AIを活用したオブザーバビリティプラットフォームが必須となりつつあります。これは、確率的な動きをするAIモデルが動的な分散環境に依存しており、従来の監視では把握が困難な形で障害を引き起こす可能性があるためです。AIを大規模に導入する組織では、コードの追跡やインフラストラクチャの監視にとどまらない、より深いレベルのシステム洞察が必要です。場合によっては、AIをモニターするためのAIの導入が求められます。レポートによると、オブザーバビリティの需要を押し上げている最大の要因はAIテクノロジーの導入であると回答している経営陣は45%に上ります。
これらリーダーはまた、インシデント対応の向上に最も貢献するAIの機能を挙げています。上位3つの機能は以下のとおりです。
- AI支援型トラブルシューティング(38%)
- 根本原因分析(RCA)の自動化(33%)
- 予測分析(32%)
これらの機能を活用することで、チームは問題がユーザーに波及する前に診断し、防止できるようになります。AIは問題の早期検出と自動対応を通じて、ダウンタイムを減らしつつ、復旧時間を短縮することができます。その結果、チームはシステム停止への事後対応から脱し、問題の事前対策を講じることが可能になります。
オブザーバビリティの具体的なビジネス価値
レポートは、オブザーバビリティがビジネスに具体的な影響をもたらすことを明確に示しています。深刻なシステム停止に伴うコストの中央値は、1時間あたり200万ドル(1分あたり約3万3,333ドル)です。フルスタックオブザーバビリティを導入している組織の場合は、この値が1時間あたり100万ドルに下がります。
オブザーバビリティはシステムの安定と信頼性に直接影響を与えます。調査では、オブザーバビリティへの投資が望ましい利益をもたらしていると報告した企業は全体の75%に上ります。約5分の1(18%)が3~10倍の投資利益率を実現していると回答しています。企業がオブザーバビリティから得られるメリットの上位は以下のとおりです。
- 予期しないダウンタイムの低減(リーダーの55%)
- 業務全体の効率化(50%)
- セキュリティ上のリスクの低減(46%)
エンジニアリングにおける効率
オブザーバビリティは、エンジニアが事後対応的な作業に費やす時間を減らし、エンジニアリングの生産性と満足度も向上させます。エンジニアが障害の「鎮火」や対応に費やす時間は全体の33%に上ります。保守や技術的負債に費やされる33%を加えると、エンジニアの業務時間のうち3分の2以上が、新機能の開発や革新的なコーディング以外の作業に費やされていることになります。
実務担当者(SRE、IT、DevOps)がオブザーバビリティから得られるメリットの上位は以下のとおりです。
- アラート疲れの軽減(59%)
- トラブルシューティングと根本原因の分析の迅速化(58%)
- チーム間連携の強化(52%)
AI支援などの機能により、オブザーバビリティワークフローが向上することで、エンジニアは問題を迅速に特定できるようになり、認知的な負荷やフラストレーションが軽減されます。その結果、チームは新機能やイノベーションに注力できるようになり、仕事への満足感が高まり、離職率の低下につながります。
課題と解決策:フルスタックオブザーバビリティとツール統合
メリットはあるものの、組織は真のフルスタックオブザーバビリティ(FSO)の実現に苦慮しています。驚くべきことに、調査対象となった組織の73%がフルスタックオブザーバビリティを未導入であり、技術スタックの大部分で包括的な監視が行われていませんでした。このギャップは事業リスクと財務リスクを引き起こします。フルスタックオブザーバビリティとは、インフラストラクチャ、アプリケーションおよびサービス、セキュリティ監視、デジタル エクスペリエンス モニタリング(DEM)、ログ管理という5つの主要カテゴリにおける可視化の実現を指します。
フルスタックオブザーバビリティの実現に伴う主な課題は以下のとおりです。
- 複雑な技術スタック(リーダーの36%が回答)
- 監視ツールの多さやデータのサイロ化(29%が回答)
新しいサービスやフレームワークがより多くのテレメトリーを生み出し、それが未連携のツールに分散されることから、これらの問題はしばしば同時に発生します。システムの健全性の可視性が断片化した結果、エンジニアは複数のダッシュボードを切り替えながらインシデントの全容をつなぎ合わせる作業を余儀なくされ、その間、重要なデータは隠れたままになります。さらに、一貫性のないテレメトリーにより、AI機能の有効性が制限されます。
幸いなことに、組織はこの問題に積極的に取り組んでいます。組織あたりのオブザーバビリティツールの平均数は、6個から4.4個へと過去2年間で27%減少しています。この傾向は、ツールの乱立がデータの断片化、オーバーヘッドの増加、インシデント対応の遅延といった問題を招くという認識を反映しています。
組織の過半数(52%)が今後12~24か月以内にオブザーバビリティツールを単一のプラットフォームに統合すると計画しています。これは、個別のソリューションから、システムの健全性を一元的かつ包括的に可視化する統合プラットフォームへの移行という、業界の強い傾向を浮き彫りにしています。
2025年以降に向けた戦略的優先課題 🚀
調査結果により、ITおよびデータ分野のリーダーが取り組むべき3つの戦略的優先課題が明らかになりました。
- システム健全性を一元的に可視化する統合プラットフォームを重視する。これにより、ツールの分散に対処し、包括的な洞察を得られるようになります。
- オブザーバビリティ駆動型の文化を育む。これにより、信頼性が共通の責任となります。
- AIを活用し、事前対応型の運用を実現する。これにより、チームの姿勢が受動的から予測的へと移行し、問題を発生前に防げるようになります。
今後のオブザーバビリティでは、予測行動、AI、レジリエンスが焦点となります。AIアプリケーションがビジネスの中心となるこの新時代では、統合オブザーバビリティのアプローチが不可欠となります。
2025年オブザーバビリティ予測の全文をダウンロードして、次のイノベーションの波に向けて万全に備えましょう。
本ブログに掲載されている見解は著者に所属するものであり、必ずしも New Relic 株式会社の公式見解であるわけではありません。また、本ブログには、外部サイトにアクセスするリンクが含まれる場合があります。それらリンク先の内容について、New Relic がいかなる保証も提供することはありません。