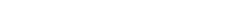

利用用途
全国61,200事業所を超える介護・福祉施設で利用される「ワイズマンシステムSP」のユーザー体験をNew Relicのカスタムダッシュボード上で可視化し、ハイブリッドクラウド環境から提供されるサービスの品質を改善
New Relicの導入目的と成果
- 介護・福祉の現場を支える「ワイズマンシステムSP」のユーザー体験を定量的に把握
- ハイブリッドクラウド環境から提供されるサービスの問題解決を迅速化
- トラブルシューティング能力が向上し、運用ベンダーと対等な立場で円滑に連携
- 「カスタム属性機能」を活用して観測データとユーザー情報を紐づけ、全国61,200事業所の端末ごとのユーザー体験を可視化
- データベースの負荷状況や遅延などを詳細に把握し、問題が顕在化する前に対処可能に
- トランザクション量と負荷の傾向などを分析し、予兆検知・予防保守の取り組みに着手
- GameDayを開催し、新たな気づきを得てオブザーバビリティの活用を深化
利用製品
- New Relic APM
- New Relic Infrastructure
- New Relic Synthetics
- New Relic Logs
- New Relic Dashboard
- New Relic Alerts
- Errors Inbox
- Workloads
- AWS / F5 / NGINX Monitoring Integration
岩手県盛岡市を拠点とするワイズマンは、医療機関や介護・福祉施設向けの業務ソフトウェア/システムを開発・提供するICTソリューション企業である。同社の中核事業であるクラウド型介護システム「ワイズマンシステムSP」は、全国61,200事業所を超える介護・福祉施設で導入され、業界トップクラスのシェアを誇る。開発本部 技術統括部 部長の佐山国央氏は次のように話す。
「ワイズマンは、医療と介護・福祉の分野に特化したICTソリューションの企画・開発・販売・サポートを一貫して手掛けています。介護報酬請求や利用者管理などの業務を支援する『ワイズマンシステムSP』は、お客様の声をお聞きしながら着実に機能を磨き上げてきました。介護にかかる記録業務をスマートデバイスから行える『すぐろくシリーズ』との自動連携も可能で、現場に寄り添った使いやすさと効率性が高く評価されています」
介護保険制度では数年ごとに報酬改定や制度改正があるが、ワイズマンシステムSPは法改正に迅速かつ確実に対応しユーザーの信頼を獲得している。
「2005年、それまでオンプレミス中心だった介護システムにおいて、私たちは業界で最も早くクラウド型サービスを開始しました。それから20年余、地震や水害といった自然災害への耐性の高さを含め、クラウド型サービスのメリットが多くのお客様に受け入れられて、『ワイズマンシステムSP』は日本全国で数多くの介護・福祉の現場を支えています」(佐山氏)

開発本部 技術統括部 部長 佐山国央氏
ワイズマンの開発本部は、技術統括部、福祉開発部、医療開発部、システム企画部、クラウドソリューション開発部の5部門から構成されるおよそ250名のエンジニア組織だ。
「技術統括部は、ワイズマンが提供する多様なアプリケーション群を開発・稼働させる基盤整備とともに、サービス基盤であるマネージドクラウド/パブリッククラウドの運用保守を担っています。私たちは2022年にオブザーバビリティプラットフォームNew Relicを導入し、お客様のサービス体験の観測を通じて様々な課題を解決しながら、プロダクトとサービスの品質向上に取り組んでいます」(佐山氏)
ハイブリッド環境におけるユーザー体験を可視化
「ワイズマンシステムSP」のサービス基盤は、日鉄ソリューションズのマネージドクラウドabsonneとAmazon Web Services(AWS)から構成される。New Relicは、このハイブリッド環境におけるユーザー体験の可視化、問題検知と原因の特定、解決の迅速化など、モニタリングの高度化に威力を発揮している。
「New Relicを導入した最大の狙いは、ワイズマンシステムSPにおける『お客様のサービス体験の可視化』です。お客様から問合せをいただいて、初めて遅延が発生していることを知るような状況を解決したかったのです。サーバーの死活監視やリソース監視といった従来のモニタリング手法では検知できない『お客様が体験する遅延や不具合』をいち早く把握し、サービス品質を高めてお客様満足度を向上させることを目標としました」と佐山氏は話す。
New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では46%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。
「New Relic導入と並行して、『ワイズマンシステムSP』のモノリシックな構造を見直し、APIを介して動作するモダンなアプリケーションに改修する作業を進めてきました。これにより、New Relicで観測できる範囲を大きく広げ、アプリケーションパフォーマンス監視でユーザー体験を可視化するとともに、より高度なインフラ監視、外形監視の自動化、といったメリットを手に入れることができました」(佐山氏)
New Relic APM(Application Performance Monitoring)は、ページ表示やAPIレスポンスなどの処理時間をリクエスト単位で可視化するとともに、データベースクエリやAPI応答時間といった遅延の原因を特定できる。
「お客様体験に影響するエラーを把握できることも重要です。お客様から『動作が遅い』と指摘される前に、問題解決に着手できるようになったことは大きな変化であり成果です。また、何らかの不具合が検知されたとき、その原因がabsonne側かAWS側なのかを切り分ける上でもNew Relicは有効です。日鉄ソリューションズとはNew Relicのダッシュボードを共有しており、協力して問題解決にあたることも可能になりました。New Relicの活用習熟が進み、経験値が蓄積されるにつれて、社内のトラブルシューティングのスキルが大きく高まったと自負しています。日鉄ソリューションズとの円滑なコミュニケーションにもつながっていますね」(佐山氏)
観測データと契約IDを紐づけたカスタムダッシュボード
New Relicは、技術統括部 インフラソリューション開発課を中心に活用が進められており、独自の視点が織り込まれたダッシュボードが次々と開発されている。運用監視に携わる佐竹隆夫氏(インタビュー時はオンラインにて参加)は次のように話す。
「定型的な情報を見るためのダッシュボードがあり、SREが不具合の調査に利用するダッシュボード、アプリケーション開発チーム専用のダッシュボードなど、それぞれの立場で見たい情報を見やすい形で配置した環境を整備しています。アプリケーションのエラーログとインフラのリソース消費を時系列で比較するなど、New Relicの観測データをNRQL(New Relic Query Language)で自由に抽出して、自由にダッシュボードをデザインできるメリットが非常に大きいと感じています」
New Relicは、ワイズマンのSREチームに新たな「分析力」をももたらした。SREチームの藤村龍氏は「PCのスペックやネットワーク帯域など、お客様ごとに異なる多様な環境で最適なサポートを提供するために、ワイズマン独自の視点でお客様の体験を把握できないかと考えた」と話しつつ次のように続けた。
「ワイズマンシステムSPは全国61,200事業所を超える介護・福祉施設で利用されていますが、お客様の『端末単位』でサービス体験を把握できる環境を整えました。New Relicの『カスタム属性機能』と『New Relic Query Language(NRQL)』を利用し、観測データと契約情報・端末仕様などを紐づけてお客様ごとのダッシュボードを生成する仕組みです」
New Relicの観測データの活用法とデータ分析の効率化を検討する過程で、SREチームとアプリケーション開発チームがアイディアを出し合ってこの環境が作り上げられた。
「たとえば、何らかの遅延が観測されたとき、全国61,200事業所において『特定のお客様がどんな体験をしているのか』『その体験は端末の仕様に依存するのか』『地域ごとに差があるか』『契約数と関連性があるか』などを分析できます。New Relicの観測データを有効に活用するアプローチとして、さらに進化させていきたいと考えています」(藤村氏)

開発本部 技術統括部 インフラソリューション開発課 エキスパート 藤村龍氏
スロークエリを数時間で解決
New Relicが、ユーザー体験を起点に、アプリケーションの挙動、データベースの負荷や遅延までを一貫して観測可能にしたことで、トラブルシューティングの大幅な迅速化が図られたという。SREの組木直人氏は次のように話す。
「従来の環境で丸ひと月を要したスロークエリの原因特定と解決を、New Relicでは数時間に短縮できた例もあります。膨大なログを解析して原因を解明するのは、熟練エンジニアにとっても難題です。たとえば『データベースそのものに問題がある』という先入観から調査に入ってしまうと、本質的な問題に辿り着くまでに時間を要すこともあります。New Relic APMでは、どのSQLが遅いのか、どのコードから呼ばれているかが一目瞭然となるため、迷わず問題解決を進められるようになりました」
SREチームとアプリケーション開発チームがNew Relicのダッシュボードで観測データを共有し、共通認識をもって対処できるようになった効果は大きい。
「さらに、SREだけでなく、アプリケーション、データベース、ネットワークなど様々なエンジニアがNew Relicの観測データにアクセスできるようになったことで、開発本部内での『情報格差』は一気に解消されました。欲しい情報が即座に手に入るため、それぞれのエンジニアが迅速に適切なアクションを起こすことが可能になったのです」(組木氏)

開発本部 技術統括部 インフラソリューション開発課 エキスパート 組木直人氏
「より良いサービスの提供」に責任を持つ
ワイズマンのエンジニア組織、中でもSREチームには、新しいテクノロジーを自ら学び、試し、活用する文化が定着化している。組木氏は次のように話す。
「New Relicで作成したダッシュボードを外部公開できる『Public Dashboard』を使って、お客様と接する支店やサポートのスタッフに効果的に情報共有を行う仕組みを検討しています。問題が顕在化する前にその可能性を共有し、お客様と適切にコミュニケーションして対応に先手を打つことが狙いです。お客様のワイズマンに対する信頼や期待を高めるために、New Relicを活用していきたいと考えています」
予兆検知・予防保守は、SREチームの中でも注力すべきテーマとして認識されている。
藤村氏は、「New Relicにより傾向分析は容易になりましたが、多くの情報から何らかの予兆を検知するには熟練が必要です。こうした領域でAI機能のサポートが受けられると、New Relic活用によるビジネス効果はさらに高められると期待しています」と話す。佐竹氏も、「観測データの分析からそれに続く自動対応まで、New Relicで利用できるAI技術の進化に期待するところは大きい」と続けた。
「顧客体験とサービス品質の定量的な把握」を目的に導入されたNew Relicは、活用開始から2年を経て開発本部にしっかりと定着化した。佐山氏は次のように結んだ。
「お客様により良いサービスを提供したい、それを実現するためのシステムの監視運用には自分たちで責任を持って取り組んでいきたい、というのがSREチーム全員のモチベーションです。お客様体験に影響する不具合を自ら調査して解決するために、そして不具合の予兆を捉えて顕在化する前に対処するためにも、New Relicは私たちに欠かせないツールです。New Relic日本法人には、ワイズマンのビジネス成長を支える技術サポートと、オブザーバビリティ機能のさらなる進化を期待しています」
コラム:「GameDay」が全体のスキルアップと新たな気づきを促進
オブザーバビリティの普及によって各部門が「情報格差」をなくし、それぞれが必要なデータを可視化・共有しながら、一致団結してより高いレベルのユーザー体験を実現していくー。ワイズマンのこうした取り組みを加速させるべく、インタビューの当日にはNew Relic日本法人の主催で「GameDay」が開催された。
GameDayはNew Relic活用支援の一環であり、参加メンバーのオブザーバビリティのスキルアップや社内コラボレーションの活性化を目的とする。各3-5名のチームに分かれ、様々な障害の課題をNew Relicを活用して解決していく実践型トレーニングだ。参加者はこのイベントを通して、普段利用しない機能や、他チームによる活用方法を知る機会となり、その後の改善活動に取り入れることができる。
当日は開発本部の各部門からおよそ20名のエンジニアが参加し、4チームに分かれてチームごとに協力しながら、New Relicが提供する、基礎から応用までの障害対応の課題に取り組んだ。

実施後はチームごとの表彰に加え、独自の基準で設けられた個人賞の表彰もあるなど、活用促進を促す設計がされている。GameDay終了後、自らもイベントに参加し楽しんでいた様子の佐山氏は「一社一社のお客様をケアするための分析力を一部のエンジニアに留めるだけでなく、組織として定着させることや、組織のケーパビリティとして落とし込むことが重要であることを改めて実感した」と話しつつ次のように語った。
「普段からNew Relicを活用しているつもりでも実は知らなかった機能や、知ることですぐに業務の効率化につながるような機能が多く、新鮮な気づきに溢れたイベントでした。また、New Relic 日本法人の活用支援の手厚さも改めて感じることができました。社内で活用の習熟度が高まってきたからこそ、何でも聞けて伴走してくれるパートナーとして頼りになるなということもまた実感しています。部門間のナレッジ共有や、オブザーバビリティの価値の再発見にもつながったはずであり、今後もぜひこうした支援を続けてほしいですね」



