
利用用途
eコマース(EC)サイトや配送システムなど、生協の基幹事業を支えるシステムをNew Relicで観測し、そのサービス品質を向上。EC化率やキャンペーン頻度にも貢献
New Relicの導入目的と成果
- 商品注文用のECサイトやアプリ、配送員向けシステムなどの安定性を高め、注文から配送におよぶ宅配事業全体のサステナビリティを向上
- これまで見えていなかった端末(PCやモバイルデバイス)側でのシステム挙動やエラーを可視化し、問題の検知と対処を迅速化
- システム障害の調査が効率化され、原因特定の工数が20%低減
- 開発プロセスにオブザーバビリティを組み込み、機能リリースによる問題の発生を未然に防げるように
- 安定稼働により、キャンペーン期間も週1日から1週間連続へ拡大可能となり、組合員の満足度とEC化率の向上に貢献
- 生協の事業を支える全ビジネスプロセスの包括的な観測を少人数で実現可能に
利用製品
- New Relic APM
- New Relic Infrastructure
- New Relic Logs
- New Relic Dashboard
- New Relic Browser
- New Relic Mobile
- New Relic Alerts
生協事業のサステナビリティ向上に向けて
東海コープ事業連合(以下、東海コープ)は、岐阜・愛知・三重の東海エリア3県で活動する3つの生活協同組合(以下、生協)「コープぎふ」「コープあいち」「コープみえ」が協同で運営する事業連帯組織だ。
「未来につながるあんしん生活」をビジョンとして掲げ、「食の安全」を第一としながら、計100万人を超える3生協の組合員に毎週1回の頻度で商品を届ける宅配事業をはじめ、店舗事業やカタログ・ギフト商品事業などを手がけている。このうち中核となる宅配事業では、商品を注文する方法として「OCR用紙注文」や「電話注文」のほか、eコマースサイト「e-フレンズ」やスマートフォンアプリ「e-フレンズアプリ」を介したオンライン注文のサービスも展開している。
そうしたeコマースサイトやアプリを含めて、東海コープを構成する3生協の事業に欠かせないシステムの企画・開発・保守・運用を担っているのが、東海コープの情報システム部だ。同部のミッションについて、部長の奥村 彰規氏は「我々の大目標は東海コープを形成する3生協の事業に貢献することです。その達成に向けて、3生協の事業方針に基づきながら、それぞれのサステナビリティ(持続可能性)を高めるためシステムを整え、運用していくことを基本方針として掲げています。その方針のもと、近年ではデジタルトランスフォーメーション(DX)にも力を注ぎ、システム基盤のクラウド化やアプリケーションのモダナイゼーションなどを推し進めています」と説明する。

生活協同組合連合会 東海コープ事業連合 管理本部 副本部長 兼 情報システム部 部長 奥村 彰規氏
こうした取り組みの一環として、東海コープが生協事業のサステナビリティを高めるためのソリューションとして活用しているのがNew Relicである。
宅配事業の要所をNew Relicで観測
New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では46%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。
東海コープではNew Relicを使って、2023年5月からeコマースサイト「e-フレンズ」の観測を始動、e-フレンズのサイトやアプリをNew Relicによる観測の対象としている。さらに、2024年4月には、New Relicによる観測対象を商品配送システムと加入手続き(組合員登録手続き)をオンラインで行うためのシステムや、それと連動する組合員管理のシステムにも広げている。
New Relicによるオブザーバビリティをe-フレンズに導入した狙いについて、奥村氏は次のように説明する。
「e-フレンズのシステムは2022年に大がかりな更新をかけ、併せてモバイルアプリもローンチしました。それを機に、宅配を利用する組合員の方々の年齢層をより若い年代へと押し広げ、かつ、組合員のEC化率(e-フレンズ利用率)をアップさせて事業のサステナビリティを高めたいと考えました。その目標を達成する上では、e-フレンズのサイトやアプリのパフォーマンス維持と安定稼働が必須でした。それを実現するために必要なオブザーバビリティソリューションを探した結果、行き着いたのがNew Relicです」
奥村氏によれば、e-フレンズに対する旧来の監視の仕組みでは、システム基盤のエラーはある程度捕捉できていたものの、エンドユーザーである組合員が使う端末(PCやモバイルデバイス)上で生じたエラーはほとんどとらえられなかったという。
「端末側のトラブルが見えていなかったことから、e-フレンズのサイトやアプリを使う組合員からの指摘がなければ、システムの問題に気づけませんでした。また、トラブルの発生時にアプリケーションのログから原因を調査・特定することは可能でしたが、それには相応の工数がかかり、問題解決を速やかに図ることも難しかったといえます。そこで、端末側でのシステムの動きも含めて『システムでいま何が起きているか』を、New Relicによってリアルタイムに可視化し、問題の発生を早期にとらえたり、または未然に防いだり、システムのユーザー体験の改善に役立てたいと考えました」(奥村氏)
一方、配送システムをNew Relicによる観測の対象に加えた理由についても奥村氏はこう明かす。
「当該の配送システムは、組合員管理のシステムなどと連携しながら、配送先に関する最新情報を配送員の端末(モバイルデバイス)に表示させる仕組みです。これは、e-フレンズのサイトやアプリと同じく、『組合員にきちんと商品をお届けする』という面で、宅配事業を支える重要な仕組みですが、以前はモバイルデバイスに対する最新情報のプッシュ配信が適切に機能せず、それが配送のミスにつながることがありました。そうしたシステム上のトラブルをリアルタイムにとらえるべく、ここにもNew Relicを採用しました」(奥村氏)
システムの安定性が増し組合員満足度がアップ。キャンペーン頻度も向上
e-フレンズや配送システムへのオブザーバビリティ導入は、さまざまな効果をもたらしている。効果の1つは、システムトラブルの原因を調査・特定するスピードの向上だ。この点について、e-フレンズの開発・保守・運用パートナーであるCMC Solutions utilize IT部 シニアエキスパートのS氏は「New Relicによる可視化によって、e-フレンズのサイトやアプリの障害調査が効率化され、トラブルの検知から原因を特定するまでの工数が最大20%ほど削減されています」との説明を加える。
また、S氏と同じCMC Solutionsのutilize IT部 係長、I氏は、New Relic活用の効果について「従来は、組合員様からの問い合わせをトリガーにトラブル原因の調査を行っていましたが、今ではNew Relicのダッシュボードを通じて問題を能動的に、かつ早期に検知できるようになっています」と指摘し、こうも続ける。
「当社では現在、注文締め切り間際の時間や期間限定の商品を企画する時など、e-フレンズへのアクセス、トランザクションが集中し、システムトラブルが起きやすいときに絞ったかたちで、New Relicのダッシュボードを使った定常監視を実施しています。これにより、トラブルを早期に検知できる可能性が高められています」
加えて、CMC Solutionsでは開発のプロセスにもNew Relicのオブザーバビリティを活用している。具体的には、e-フレンズの機能を更新する際に、その実施前にNew Relicによるシステム挙動の最終チェックを行っているのだ。その効果についてS氏は「e-フレンズでは、大型(メジャー)な機能リリースを四半期に1回のペースで行い、細かな更新については月1回のペースで実施しています。New Relicを使った最終チェックによって、それらのリリースが安心して行えるようになりました。また、その最終チェックにより、機能リリースによる大きな障害の発生を未然に防げた例もあります」
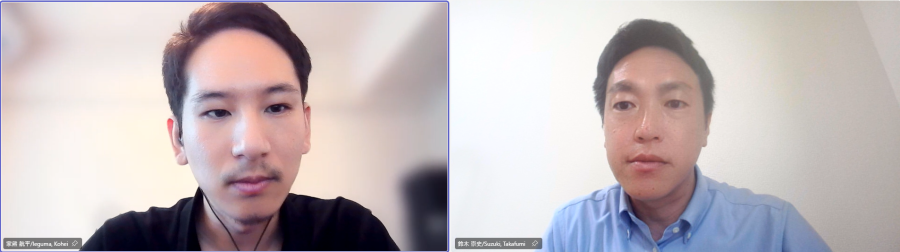
株式会社CMC Solutions utilize IT部 係長 I氏(写真左)
株式会社CMC Solutions utilize IT部 シニアエキスパート S氏(写真右)
これらの効果を踏まえながら、奥村氏はNew Relic導入の効果を次のようにまとめる。
「New Relicによるオブザーバビリティを通じて、e-フレンズや配送のシステムの安定性が増し、それが宅配事業におけるサービス品質の向上や顧客(組合員)満足度の向上につながっていると感じています。例えば、e-フレンズでは以前からサイトでしか購入できない限定商品の企画を実施していますが、アクセスの集中で画面表示がされない事象が度々発生していました。いまでは、毎日いつでも安心してキャンペーンが打てるようになり、組合員の満足感を高められています。また、現在のe-フレンズアプリのローンチ前は、当アプリに対する不満の声がSNS上で散見されましたが、いまでは、そうした不満の声もなくなりました。我々には、組合員のEC化率を現状(2025年7月時点)の40%程度から60%へ引き上げるという目標がありますが、その目標の達成にもNew Relicが有効に機能してくれています」

事業を支える全システムの包括観測へ
上述したような効果を手にした東海コープでは、New Relicによる観測対象のシステムをさらに押し広げることを計画している。
「e-フレンズや配送のシステム以外にも、生協の事業を支える仕組みはさまざまにあります。今後は、それらの観測もNew Relicによって包括的に行い、事業全体のサービス品質の向上や組合員満足度のアップ、さらにはサステナビリティの向上に役立てていきたいと思っています。言い換えれば、生協の事業を構成する全てのビジネスプロセスをNew Relicによって観測し、その品質向上に役立てていきたいということです。多様なシステムの観測を単一のプラットフォームで行えるNew Relicならば、少ない人員でも、そうした取り組みを効率的に行えるようになると期待しています」(奥村氏)



