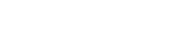利用用途
ネット証券事業の中核を成すシステムをNew Relicによって観測。システムの開発・運用に携わる全技術者が共通のプラットフォームを通じてシステムの状態を把握できる環境を築き、障害検知・対応のスピードアップに生かす
New Relicの導入目的と成果
- トランザクションのピーク時にも、障害原因を速やかに特定するための監視体制を整備
- システム知識や監視体制の属人化を防ぎ、障害対応を社内の全技術者が協力して行う体制を整備
- 複雑化・高度化するシステムをNew Relicで可視化し、障害対応を迅速化
- 外部ベンダーの工数で行っていたシステムの外形監視を内製化
- ツールのサイロ化やログ頼りを防ぎ、リソース監視からユーザー体験観測へシフト
利用製品
- New Relic APM
- New Relic Browser
- New Relic Infrastructure
- New Relic Logs
- New Relic Dashboard
- New Relic Synthetics
- New Relic Alerts
MUFGグループとしてネット証券事業への信用・信頼を確保
三菱UFJ eスマート証券は、長きにわたり、ネット証券の市場を牽引する企業として成長と発展を続けてきた。2019年からは三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)とKDDIグループが共同出資する「auカブコム証券」として事業を展開。近年も堅調に証券口座の数を増やし、2025年度(2025年3月期)も、2024年4月~2025年1月の約10カ月間で月平均約1万のペースで新規口座を獲得し、2025年1月時点の証券口座数は179万以上に達している。
そして2025年2月には三菱UFJ銀行の100%子会社となり、社名を現社名「三菱UFJ eスマート証券」へと変更し、新たなスタートを切っている。今日では「au経済圏」におけるネット証券の役割を引き続き担いながら、MUFGとの強固な繋がりを持つネット証券として一層の飛躍を目指している。
同社のシステム技術部 基盤グループでグループ長を務める池浦 將登(まさと)氏は、今回の組織的な変化の意義と意味について次のような見解を示す。
「三菱UFJ 銀行の100%子会社となり、MUFGとの繋がりが強化されたことで、当社の信用力や信頼性・安心感はこれまで以上にアップし、それは市場における差異化の源泉になっています。だからこそ、当社のシステムには、ネット証券市場で競争優位を確保するための利便性や機能の斬新さを実現することと併せて、安定した稼働を維持する必要性がかつてないレベルで高まっているといえます」
システム技術部 基盤グループ グループ長 池浦 將登(まさと)氏
こうしたビジネス上の要件を満たすための仕組みの1つとして、システム技術部全体で活用を進めているのが、2024年2月に導入したオブザーバビリティプラットフォーム「New Relic」である。
ネット証券特有の複雑構造のシステムを可視化し、ログ中心の監視体制から脱却
New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では46%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。
三菱UFJ eスマート証券が、New Relicの導入に乗り出したきっかけは同社の「新スマホシステム(現「三菱UFJ eスマート証券アプリ」のシステム)」で2023年に発生した障害だった。
この新スマホシステムは、ネット証券事業の核となるシステムで「国内株式」「米国株式」「投資信託」「先物」「オプション」「NISA」「つみたてNISA」「クレカ積立」といった各種商品の取引ができるほか、180銘柄を登録できるリアルタイム株価ボードや高機能チャート、資産状況・投資成績が一目で確認できる仕組みを提供している。
そのシステム障害が起きた当時の状況について、同社のシステム技術部 基盤グループの土屋 開(かい)氏はこう振り返る。
「新スマホシステムの障害は、証券システムへのアクセスが集中する午前9時に起きました。そのとき対応を急いだのですが、それまで頼っていたログを中心とした監視の仕組みでは、障害原因を特定し切れませんでした」
なぜ、障害原因が特定し切れなかったのか。その要因について土屋氏は次のように説明を加える。
「これは、証券のシステムに共通した課題と言えるのですが、アクセスが集中する午前9時に瞬間的に障害を発生させるリスクがあり、新スマホシステムで起きた障害は、まさにそのリスクが顕在化したものです。この種の障害は、トランザクションのピーク時など、特定の条件下で一時的に引き起こされるものだとは分かっていたのですが、なぜそれが起きたのかを特定するのが、当時の監視体制ではかなり難しかったのです。当社の新スマホシステムは、多種多様な外部システムとフロントエンドの各機能が、さまざまなAPIを介して複雑に絡まり合う構造を成しています。インフラやネットワーク、アプリケーションなどから、それぞれサイロ化された監視ツールを頼りにログを収集していたのですが、大量のログやエラーアラートを頼りにした人力による監視体制では、複雑に連携するシステムにおいて、障害発生時にどの処理が問題なのか、その原因の特定まで辿り着くことが非常に困難だったのです」

システム技術部 基盤グループ 土屋 開(かい)氏
こうした問題を抜本的に解決するソリューションとして同社が選んだのが、オブザーバビリティプラットフォームによってシステムを包括的に観測し「システムの状態(=システムで何が起きているか)」を可視化することだ。その考えがNew Relicの導入につながったと土屋氏は明かす。
もう1つ、オブザーバビリティプラットフォームの導入には、システムに関する属人性を可能な限り低減させる狙いもあった。この点について土屋氏は次のような説明を加える。
「ネット証券事業が成長するのに伴い、当社のシステム技術部の陣容も拡大し、新しい要員がどんどん増えていきました。その一方で『このシステムのこの部分は、特定の人にしか分からない』ということが多くあります。その状況は、システムの障害や改善要求への対応が特定の人にしか行えないことを意味し、組織としては避けるべき状況です。そうしたシステムの属人性を一掃する手段としても、New Relicなどのオブザーバビリティによってシステムを可視化するのが有効との判断がありました」
オブザーバビリティの機能を提供する製品は、New Relicの他にも存在する。その中でNew Relicを選んだ理由について、土屋氏はこう明かす。
「New Relicと同等の機能を提供する製品はありましたが、その製品の料金体系はサーバー(サービス)単位の課金をベースとしていて、当社の環境や目的にフィットしたものではありませんでした。当社では当初から、システムだけではなく、その開発を行うための多数のステージング環境も、本番環境と同様に観測したいと考えていました。ですので、サーバー単位の課金では料金がかなり膨らむことが予想されました。それに対し、New Relicはユーザー数やデータ転送量をベースにした分かりやすい料金体系になっていて、その点でも弊社の環境や目的に合致していました」
社内の全システム技術者へNew Relic活用を推進し、障害対応の迅速化へ
New Relicの採用を決めた同社は、2023年11月からのPoCを経て2024年2月の本格導入に至った。導入当初の観測対象は新スマホシステムに絞られていたが、のちには、PC上で株価情報やニュースを配信する投資情報ツール「kabuステーション」や法人向けAPIサービス「kabu.com API」へと観測対象を広げた。
同社では、New Relic活用における第一段階の目標を、システム技術者に対するシステムの見える化に設定している。この目標のもと、New Relicが無料で提供している「ベーシックユーザー(*1)」ライセンスを活用し、システム技術部に所属する全技術者(システムの開発、運用管理・基盤系の技術者)が、New Relicを通じてシステムの状態やイベントログを確認できる体制を整えている。
*1 ベーシックユーザー:New Relicのオブザーバビリティツールの設定、データクエリの実行、ダッシュボードの利用、基本的なアラート機能などが使用できる無料のライセンス
土屋氏は、この体制づくりの狙いを「システム障害への早期対応」に置き、こう続ける。
「これまで当社では、システムに何か問題があると、当該システムの開発チームから基盤グループにイベントログの確認依頼が来るのが標準的なフローでした。ただし、それでは初動がどうしても遅れてしまいます。そこでNew Relicという共通のプラットフォームを通じて、開発チームと基盤グループの双方がシステムの状態やログを自ら確認できるような環境づくりを目指しました。その次のステップとして障害の早期発見に向けたアラートの活用を進める予定です」

この言葉を受けて、池浦氏はこう続ける。
「New Relicの導入により、システムにかかわる技術者全員が同じデータを見ながら議論できる場が作られただけでも大きな前進であると見ています。いまのところ、当社がお客様向けに提供するシステムの一部しか観測していませんが、その対象をどんどん押し広げていきデータが揃ってくれば、開発の技術者たちもNew Relicをより積極的に使うようになり『こんなデータが見たい』『この機能が欲しい』といったニーズも出てくるでしょう。そうなれば、システム技術部がシステム上の問題に対応するスピードは自ずと上がっていくはずです」
こうした技術者によるNew Relicの活用を加速させるべく、土屋氏はNew Relicの社内勉強会も定期的に催し、「New Relic APM」の使い方や「New Relic Infrastructure」を通じたログの収集法、「New Relic Synthetic」による外形監視の方法などを指南しているという。
「この勉強会により、New Relicに対する技術者たちの理解が進み、例えば、開発の技術者が自分の担当したシステムについて、知りたいデータをNew Relicで瞬時に取得できるようになりつつあります」と土屋氏は語り、さらに「開発プロセスへのNew Relicの適用も始まり、新規システムの開発において、開発した成果物が要件を満たせているかどうかの負荷テストにNew Relicが使われるケースも出始めています」と続ける。
システム状態把握と外形監視が効率化 リソース監視からユーザー体験の観測へ
土屋氏による勉強会の効果もあり、New Relicの活用は技術者の間に着実に根づきつつある。これにより一定の効果が見られ始めていると土屋氏は言う。
「まず指摘したい効果の1つは、開発の技術者が自分の取得したいログを基盤グループの助けを借りずに取れるようなったことです。これにより、システムの状態を把握する作業がかなり楽になったとの声が、開発チームの間から聞こえています」(土屋氏)
また、同社では従来、システムの外形監視を外部の協力会社に依頼し、人手によって行ってきた。その人手による作業をNew Relic Syntheticsに置き換えたことで、外形監視を社内で効率的に完結させることが可能になったという。
これらの効果を踏まえながら、土屋氏はNew Relic活用の今後についてこう展望する。
「まずは、New Relicの観測の対象を、当社がお客様向けに提供する全てのシステムに押し広げ、かつ、新スマホシステムなどにつながる多種多様なシステムや、今後使う予定のシステムも監視の対象にしていきます。そして、最終的には1つの画面を通じて『システム上のどの処理が障害の原因になっているか』『どの処理がパフォーマンスのボトルネックになっているか』を突き止められるようにする計画です。また、障害原因を突き止めた際には、その情報をもとに随時アラートの設定を最適化し、障害の早期検知も実現していく考えです。そうした仕組みの実現に向けて、New Relicにはこれからも引き続き、他社ではありえないような手厚い技術サポートを続けていただきたいと願っています」
さらに池浦氏は、New Relicを活用して目指すゴールについてこう締めくくった。
「New Relic活用での究極的なゴールは、システムのユーザー体験(UX)を維持・向上させ、ネット証券事業に貢献することでしょう。それには、お客様が気づく前に、UXの低下につながる事象に我々が気づく必要があります。ただし、それを従来のようなシステムのリソース監視のみによって実現しようとすると、UXとはほとんど関係のないシステムの変化をとらえようとしがちになり、結果として、あまり意味のないシステム改善の努力を重ねることになります。それを避けるためにも、ユーザー体験を重視し、お客様がシステムに不満を抱く感覚的なところを可視化すべきであり、それは不可能なことではないと見ています。New Relicの活用を通じて、そうした世界を目指したいと考えていますし、そこに向けた革新的な技術の提供をNew Relicには期待しています」