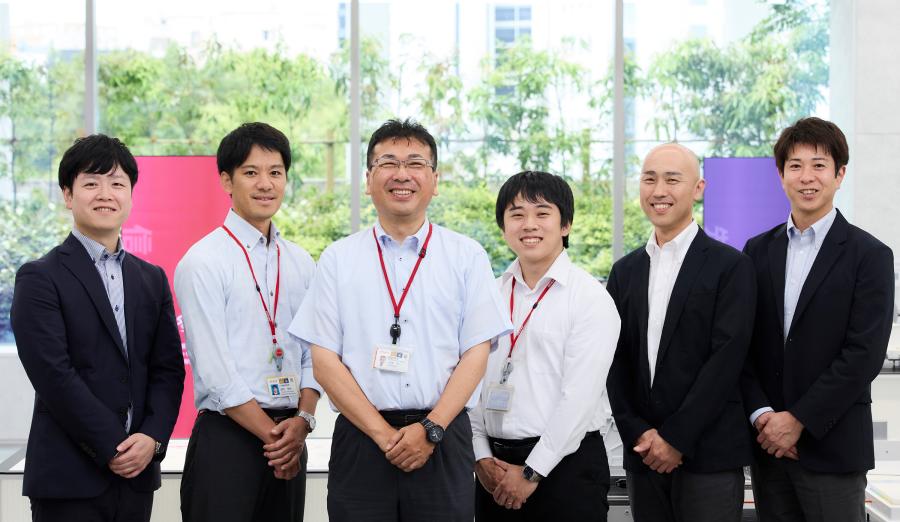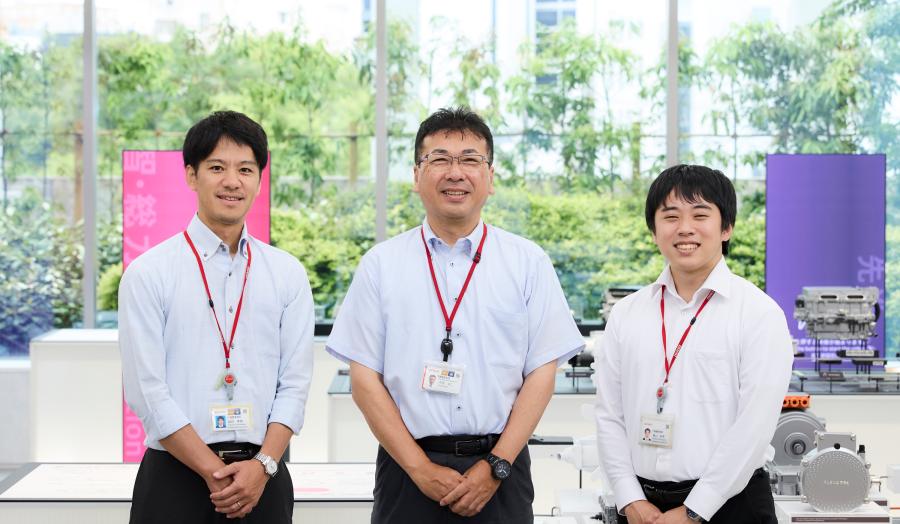
利用用途
Zabbixによるインフラ監視を補完するためにオブザーバビリティを導入、自社開発アプリケーションのパフォーマンス問題の解決を起点に他システムへ展開、将来のハイブリッド/マルチクラウド環境の統合監視を目指す
New Relicの導入目的と成果
- クラウドリフト/シフトに伴う分散化と複雑化に適応するためのモニタリングのモダン化
- オンプレミス環境のインフラ監視を担うZabbixをNew Relicで補完
- New Relicがシステムとアプリケーションプロセスを可視化し、高難度の問題解決を迅速化
- 熟練エンジニアでも3日間を要するパフォーマンス問題の原因特定を3時間で実現
- グループ従業員2万ユーザーが利用する承認申請システムの性能問題の原因特定と改善
- New Relicの活用高度化と、理想的なシステム運用監視への歩みをパートナーのSCSKが伴走支援
利用製品
- New Relic APM
- New Relic Infrastructure
- New Relic Dashboard
デンソーは、モビリティエレクトロニクス、サーマルシステム、パワートレインシステム、電動化システムを中心に、クルマの進化を支える先進的な製品・システムを提供するグローバル企業である。「統合報告書2024(2024年3月期)」では、デンソーの存在意義と果たすべき目的を「環境・安心の軸で社会課題を解決すること」と定義し、これを実現するための新たな指針が示された。IT基盤推進部 ITサービス室長の木原祐二氏は次のように話す。
「デンソーは『DX銘柄2025』に初めて選出されました。モビリティ領域ではソフトウェア開発工程の自動化とAI活用が、新規事業領域ではカーボンクレジットの創出に寄与する森林管理のデジタル化への取り組みがそれぞれ評価されました。いずれも『環境・安心』領域でのデジタル活用が実を結んだ形です。私たちIT基盤推進部は、先進テクノロジーの提供と基盤整備を通じて、経営戦略と一体化したデジタル変革をさらに加速させていきます」

株式会社デンソー IT基盤推進部 ITサービス室長 木原祐二氏
IT基盤推進部は、グローバルに展開するデンソーグループおよそ140社が利用するITインフラの整備と運用を担っている。オンプレミスの仮想化基盤とAWSやAzureなどのパブリッククラウドの安定稼働を維持することが最重要のミッションだ。基幹システムだけでもおよそ3,000OSという大規模な環境である。IT基盤推進部 ITサービス室 サーバサービス2課長の嶋岡孝典氏は次のように話す。
「オンプレミス環境は、Zabbixによる統合的な監視システムを整備し、サーバーやネットワークの死活監視、インフラリソース監視を中心に日々の運用を行っています。一方、クラウド監視にはCloudWatchやAzure Monitorといったツールを利用してきました。デンソーでは全社方針としてクラウドへのリフト/シフトを加速させており、システムの分散化と複雑化が今後いっそう進んでいくことは明らかです。私たちは、急速に進む環境変化に対応するためオブザーバビリティ技術の検証に着手しました」

株式会社デンソー IT基盤推進部 ITサービス室 サーバサービス2課長 嶋岡孝典氏
2024年6月、オブザーバビリティプラットフォームNew RelicのPoC(概念検証)が始まった。サポートしたのは、デンソーの長年にわたるITパートナーであり、New Relic製品とエンタープライズ領域のシステム運用に精通したSCSKである。
システムの「体感が遅い原因」を即座に可視化
New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では46%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。SCSKは「SCSK Plus サポート for New Relic」のもと、New Relicを導入・活用するためのコンサルティングから、PoC、構築・運用支援、トレーニングまで一貫したサービスを提供する体制を整えている。
「New Relicは、クラウドネイティブな環境を監視する上でも、オンプレミス環境の問題解決を迅速化する上でも非常に有効です。たとえばシステムで遅延が発生したときに、New Relicなら『なぜ体感が遅いのか』『その原因はどこか』を速やかに可視化することができます」とSCSK ITインフラサービス事業グループ 基盤ソリューション事業本部の阿比留真人氏は話す。

SCSK株式会社 ITインフラサービス事業グループ 基盤ソリューション事業本部 モビリティサービス部 第一課 阿比留真人氏
既存の監視ツールで「システム遅延」の原因を特定するには、熟練エンジニアでもログ解析に多大な工数を要していたという。木原氏は次のように振り返る。
「New Relicの第一印象は『これはいい、使える』というものでした。New Relicなら、エージェントを入れるだけで基本機能がすぐに使えて、遅延の原因がスロークエリなのか、メモリリークなのか、同時アクセスの急増なのかを調査できます。経験の少ないエンジニアでも使いこなせば大きな武器になると確信しました。私たちにとってより重要なのは、New Relicが示した『なぜ体感が遅いのか』『その原因はどこか』に対して、『どう対処すべきか』をSCSKがサポートしてくれる体制が整えられたことです」
2万ユーザーが使うシステムの性能問題を解決
IT基盤推進部では、入念な機能検証・評価を経て、デンソーグループの従業員およそ2万ユーザーが使う「申請承認システム」のトラブルシューティングにNew Relicを適用した。このシステムでは特定の曜日や時間帯に遅延が発生し、業務への影響が無視できないほどになっていたという。問題解決に取り組んだIT基盤推進部 ITサービス室 サーバサービス2課の福山裕幸氏は次のように話す。
「申請承認システムは、Javaアプリケーションサーバーとパッケージ製品により構成されており、遅延の原因がどこにあるのか既存の監視ツールでは特定が困難でした。ログと格闘して経験と勘を頼りに原因究明に取り組むしかなかった状況が、New Relicの導入で一変しました。アプリケーションプロセス全体が可視化され、遅延の原因を容易に絞り込むことが可能になったのです。私たちはNew Relicを活用して調査を進め、可視化されたアプリケーションの健康状態を探っていくことで、原因のひとつとしてフルガベージコレクションが1日数回発生していることを突き止めました」

株式会社デンソー IT基盤推進部 ITサービス室 サーバサービス2課 福山裕幸氏
福山氏が利用したNew Relic APM(Application Performance Monitoring)は、アプリケーションのレスポンスタイム、スループット、エラーレート、トランザクションなどを可視化し、コードレベルにまで踏み込んだ原因調査が可能だ。
「熟練エンジニアでも丸3日を要するような難しい問題でしたが、New Relicを利用することで、わずか3時間で原因を特定することができました。ユーザー体験を可視化・定量化して問題解決に結びつけるNew Relicとオブザーバビリティの威力を、まさに実感させられた事例です」と嶋岡氏は話した。
ハイブリッド/マルチクラウドの統合監視に期待
IT基盤推進部は、「承認申請システム」での可視化=健康診断の効果を他のアプリケーションにも広げていく考えだ。「活用事例を共有するなど、アプリケーションチームにNew Relicへの関心を高めてもらえる活動も進めていきたい」と嶋岡氏は話し次のように続けた。
「New Relicのライセンス体系は、少人数で使い始めて段階的にユーザーを拡大していく私たちのケースに最適でした。今後は、アプリケーションチームにライセンスを提供することで、開発エンジニアが自ら問題検知や原因特定を行える体制を整えていきたいと考えています」
ユーザー数と取り込んだ観測データ量でコストが決まるNew Relicの「ユーザーライセンス」は、コストを見通して予算計画に適合させやすいメリットもある。
「現時点ではZabbixによるインフラ監視をベースにしつつ、難易度の高い問題の解決にNew Relicを活用していくことを想定していますが、目標はあくまでも『分散化と複雑化が進むシステムに適応するためのモニタリングのモダン化』です。その先には、クラウドネイティブ環境への適用、ハイブリッド/マルチクラウド環境の統合監視の実現を見据えています」(嶋岡氏)
福山氏は、「今後、クラウドへのリフト/シフトがさらに進んだときに、New Relicの真価が発揮されるものと期待しています。New Relicの外形監視は、ブラックボックスの多いSaaS/PaaSの正常性の確認にも有効です。対象システムの所在を意識することなく、オンプレミスとクラウドをNew Relicのダッシュボードから統合的にモニタリングできることが、次世代の監視システムとしてのひとつの理想形ではないでしょうか」と続けた。
SCSKはデンソーのアプリケーション開発もサポートしており、「今後は開発段階でもNew Relicを活用し、アプリケーションの品質向上に結びつけていきたい」(SCSK阿比留氏)と期待を示す。
木原氏は「New Relicには徹底的に尖ってほしい」と話しつつ次のように結んだ。
「『なぜ体感が遅いのか』『その原因はどこか』『どう対処すべきか』に、一貫してNew Relicが答えを示してくれるような進化にまずは期待しています。AIOpsがさらに進んで監視・運用が自動化されるのも、遠い将来の話ではないでしょう。SCSKには、目の前のNew Relic活用の高度化を引き続き支援していただきながら、デンソー全体視点でシステム運用を考えたときの理想像を私たちと一緒に追究してもらえることを願っています」