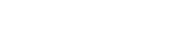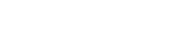

利用用途
AI食事管理アプリ『あすけん』のモバイル/バックエンドアプリケーションの内製化とモダン化を進め、より顧客価値の高い機能の迅速な開発・実装、より良い顧客体験を追求するためにNew Relicを活用
New Relicの導入目的と成果
- 『あすけん』の内製化とモダン化の推進に欠かせないシステムとアプリケーションの可視化
- DevOps推進のための「監視やアラート運用の民主化」からオブザーバビリティの活用を定着化
- 「ダッシュボードコンテスト」を通じて、エンジニア全員のNew Relic活用スキルを向上
- 問題検知、原因究明と解決、プロダクトの品質向上にエンジニア組織全員で取り組む文化の定着化
- 今後のビジネス成長を支えるリアーキテクチャの着実な推進
- 熟練エンジニアが作成したメトリクスを初学者が学習・体得する全員成長サイクルで「自走式オブザーバビリティ」を実現
利用製品
- New Relic APM
- New Relic Mobile
- New Relic Dashboard
- New Relic Logs
- Errors Inbox
- Change Tracking
「カロリーや栄養素を自動で計算」 「管理栄養士監修のアドバイスが届く」――ダイエットや健康管理への確かな効果が評判を呼び、AI食事管理アプリ『あすけん』の人気は伸び続けている。ダウンロード数・売上・アクティブユーザー数は4年連続で国内No.1*、2025年10月には累計会員数が1,300万人を超えた。エンジニアリングマネージャーとしてプロダクト開発を率いる西秀和氏は次のように話す。
「AI食事管理アプリ『あすけん』は、ユーザーさんにとって身近な専属栄養士のような存在です。スマートフォンで食事を撮影したり食品のバーコードを読み取るだけでカロリーや栄養素が表示され、自分に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素の過不足が一目でわかります。さらに、管理栄養士が監修した食生活へのアドバイスの提供を通じて、健康的な食生活の実現をサポートします」
askenの会社設立は2007年。『ひとびとの明日を今日より健康にする』というミッションを掲げ、栄養学の知見、100億件以上の食事記録データ、AIなどのテクノロジーを融合させ、顧客価値の高い食事管理サービスを提供し続けている。

「ダイエット、ライフステージに応じた栄養バランス管理、健康増進など、『あすけん』の利用目的は様々ですが、20〜30代の女性を中心に幅広いユーザー層へ支持が広がっています。大きな特徴は、栄養士キャラクター『未来さん』による食生活へのアドバイスです。管理栄養士が監修した20万件以上のパターンから最適なアドバイスを提供する仕組みで、これがユーザーの食生活や行動に変化を促し、結果としてダイエットや健康管理に効果をもたらします」と西氏は話す。

プロダクト開発本部 プロダクト開発部 エンジニアリングマネージャー 西秀和氏
『あすけん』は、1,200万会員の達成からわずか6カ月で新たに100万会員を獲得した。こうした急成長の裏では、モバイル/バックエンドアプリケーションのモダン化が着実に進められている。
「さらなるビジネス成長を支え、より顧客価値の高いサービス開発をスピード化するために、内製化を軸にシステムのモダナイゼーションに着手したのは2023年です。プロジェクト開始とともにオブザーバビリティプラットフォームNew Relicの活用を本格化し、優れた可視化・定量化の機能を活用して、システム監視・保守の高度化とDevOpsの推進に力を注いでいます」(西氏)
「監視・アラート運用の民主化」によるDevOps文化の加速
New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では48%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。インフラエンジニアとして、プロダクト開発部における「オブザーバビリティの定着化」に尽力した鈴木一帆氏は次のように話す。
「2023年の時点では、New Relicを使いこなせるエンジニアは限られており、エンジニア組織全体を見渡してもオブザーバビリティへの意識は決して高くなかったと思います。その背景には、監視・アラート運用がインフラエンジニアなど固定メンバーに限定されていたこともありました。システムエラーへの対応がその場限りになってしまい、根本的な原因究明や改善が先送りになっていたことも事実です。システムのモダナイゼーションの推進と同時に、監視・アラート運用を誰でも行えるよう『民主化』することがDevOps文化の推進には重要です。そこで、まずは機能リリース後のエラー監視やモニタリングから始めようということで、インフラ・バックエンド・モバイルの各部門でNew Relicの活用を定着化していきました」

プロダクト開発本部 プロダクト開発部 インフラエンジニア 鈴木一帆氏
各部門で機能リリース後の監視やエラー改善の取り組みは進んだが、それでもNew Relicで「何ができるのか」を理解し、実際に活用できる、または積極的に活用するのはエンジニア全体のうち、2〜3割のメンバーに留まっていた。「New Relicの製品理解を浸透させ、エンジニアにこのツールの良さをわかってもらい、利用率を押し上げるには、何かきっかけが必要だと考えていました。目指していた『運用の民主化』のためには、エンジニア組織全体でNew Relicの活用スキルを底上げすることが重要と考えました(鈴木氏)」
「ダッシュボードコンテスト」を通じてNew Relic機能を体感
「エンジニア組織全員がNew Relicを使えるようにしたい」「単なる勉強会ではつまらない」と考えた西氏、鈴木氏らは、New Relic日本法人のアカウントチームと協力して企画を練り上げた。その成果が、モバイルとバックエンドのロール横断でチームを編成し『最強のNew Relicダッシュボード開発を競うコンテスト』である。
「New Relicに触れる機会のないエンジニアも多かったので、ダッシュボード開発を通じてNew Relicの機能を体感してもらうことを重視しました。『オブザーバビリティ成熟度モデル』で規定する項目を採り上げ、システム障害、コードの高品質化、技術負債の解消、リリースの迅速化、ユーザー行動の可視化それぞれへの貢献度を軸に、技術点・構成点・芸術点で総合評価する仕組みを考案しました」と西氏は話す。
コンテスト当日は、90分の持ち時間で4チームが実際にNew Relicのダッシュボードを構築した。ログから抽出した文字列から動的にグラフを表示させる、テンプレート変数を使ってダッシュボードをカスタマイズする、障害対応とビジネスKPIを見やすく表示するなど、それぞれのチームから工夫を凝らしたダッシュボードが披露された。
「コンテストということで競争意識が働き、それぞれのチームがコンセプトづくりから基本設計までを事前に済ませた上で本番に臨みました。優勝したのは、『使われていないAPIを一覧表示する』というユニークな視点でダッシュボードを構築したチームです。テレメトリーデータがない条件下で一覧表を作成するために、ルックアップテーブルを用いてNRQL(New Relic Query Language)で結合するという独創性を評価しました」と鈴木氏は話す。
エンジニア組織の全員が参加した「ダッシュボードコンテスト」は、西氏、鈴木氏らが狙った以上の成果に結びついたという。New Relicの定常的な活用率は、コンテストを実施しただけでそれまでの2〜3割から8割のエンジニアへと急拡大し、利用機能数も目に見えて増加した。
「見えなかった情報が見えるようになって、エンジニアの意識と行動が変わりました。何らかのアラートが発信されたとき、『最初にNew Relicのダッシュボードを確認』する習慣がエンジニア組織全体に定着化しました。システムで『何が起こっているのか』を正確に把握した上で、『どんな打ち手が必要か』を考えて必要なアクションを起こす、という流れも出来上がりつつあります」と鈴木氏は手応えを示した。
New Relicを活用しリアーキテクチャを推進
プロダクト開発部では、『あすけん』の中長期的なビジネス成長を見据えて、アーキテクチャの刷新を伴うアプリケーションの再構築が急ピッチで進められている。バックエンドシステムのモダン化に取り組む多田俊介氏は次のように話す。
「PHPで構築されたAPIをKotlinを用いて刷新するプロジェクトは、私にとって大きなチャレンジでした。New Relicによる定常的なモニタリングをベースに、リリース前後でのメトリクスの比較などを通じて、『気づくべき問題に気づける環境』を利用できたことにかなり助けられたと思います。リリース後に、APIの性能が狙い通り出ているか、データベースの負荷が下がっているかも正確に把握できるようになりました」
多田氏は、日々の運用ではNew Relicの「Errors Inbox」を使って常にエラーを監視・追跡し、「すぐに対処すべき問題なのか、既知の問題なのかを速やかに切り分けて、優先度に応じて適切に対応できるようカスタマイズしている」という。

プロダクト開発本部 プロダクト開発部 バックエンドエンジニア 多田俊介氏
バックエンドと歩調を合わせて、モバイルアプリの最新化も着実に進む。モバイルエンジニアの三浦渚氏は次のように話す。
「モバイルアプリでは、最新のモバイルOS/プラットフォームに最適化されたUI/UXを実現することに常に気を配っています。これを実現するための技術課題を解決するとともに、アプリの開発生産性を向上させるKMP(Kotlin Multiplatform)への取り組みも進めています」
2025年に入り「課金ライブラリ」の移行プロジェクトが始まった。『あすけん』の収益の柱であるアプリ内課金を実装するAPIの最新化だ。
「New Relicのダッシュボードをカスタムメイドして、どんなエラーがどこでどれだけ発生しているか、課金ライブラリの移行前後での差異をリアルタイムで把握できるようにしました。New Relic APMで原因を探りながら改善を進めつつ、サービス影響のある不具合を観測したときはChange Trackingを確認して速やかに切り戻しを行ったこともありました」(三浦氏)

プロダクト開発本部 プロダクト開発部 モバイルエンジニア 三浦渚氏
エンジニア組織全員で、ユーザー体験の向上に挑む
『あすけん』のリアーキテクチャへの取り組みとともに、システムエラーや不具合の抜本的な解決は着実に進展している。懸案だったデータベースの性能問題の解決にもNew Relicが活用されたという。
「現在のチャレンジは、エンドツーエンドのユーザー体験の把握と性能の最適化です。モバイル端末とアプリ、APIとバックエンド、データベース、サーバー、ネットワークといった、ユーザー体験に影響する要素を一貫して把握するところから着手しています。今後マイクロサービス化が進んでいく中で、パフォーマンスボトルネックの特定はさらに難しくなっていきますが、New Relicの分散トレーシングを活用しながらこの難題を突破していきたいと考えています」(鈴木氏)
NRQLを生成AIで記述して、思い通りのダッシュボードを作成する取り組みも始まっている。
「生成AIとNRQLは非常に親和性が高いと感じています。New Relicは、NRQLで操作できるメトリクスの幅が広いので、より柔軟に目的に応じたダッシュボードを作成できます」と鈴木氏は言う。
さらに、「New Relicの良いところは、メトリクスの意味やその作られ方を内部で調べることができ、それらを他のエンジニアが参照することで、エンジニア全員がメトリクスの知識についてベースアップできることです」と西氏は付け加える。
「熟練のエンジニアが作成したメトリクスを初学者がNew Relicを通して学び、内容や技術、特定の問題があった際の監視の勘所を含めて理解し、次回から自分のものとして活用するサイクルを回すことで、エンジニア全員の技術レベルの底上げにつながっています。自走式のオブザーバビリティとDevOps文化の醸成につながっている重要なドライバーの一つであると言えます」(メトリクスの理解を通じたDevOps文化の醸成については、西氏が執筆したこちらの技術ブログ記事にも詳細が紹介されている。)
『あすけん』が急成長のフェーズに突入したタイミングで、New Relicの本格的な活用が始まった。そこから丸2年が経過し、西氏は大きな手応えと自信を感じている。
「この急成長期に、エンジニアリングの品質を落とさずに組織として進化を続けてこれたのは、New Relicがもたらす『分析思考の共有』や『形式知化のしやすさ』による恩恵も大きかったと思います。メトリクスの共有を軸とした社内学習サイクルはその一例であり、監視設定の自由度が高く参照しやすいNew Relicならではの利点だと感じています」
システムのモダン化の進展と歩調を合わせて、オブザーバビリティの定着化が図られたことは、プロダクト開発にとって大きな資産となっているという。
「エンジニアの誰もが、New Relicの観測データをもとに自律的に問題解決に取り組み、ユーザー体験を意識しながらプロダクトの品質を作り込めるようになりました。New Relic日本法人の技術支援を受けながら活用を進めてきましたが、現在は自分たちで学びながら活用水準を高められるまでになっています。これからも、オブザーバビリティの活用をいっそう深化させ、よりユーザー価値の高いサービスの迅速な開発と実装に結びつけていきたいと考えています」
* 日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数(2026年1月、Sensor Tower調べ)